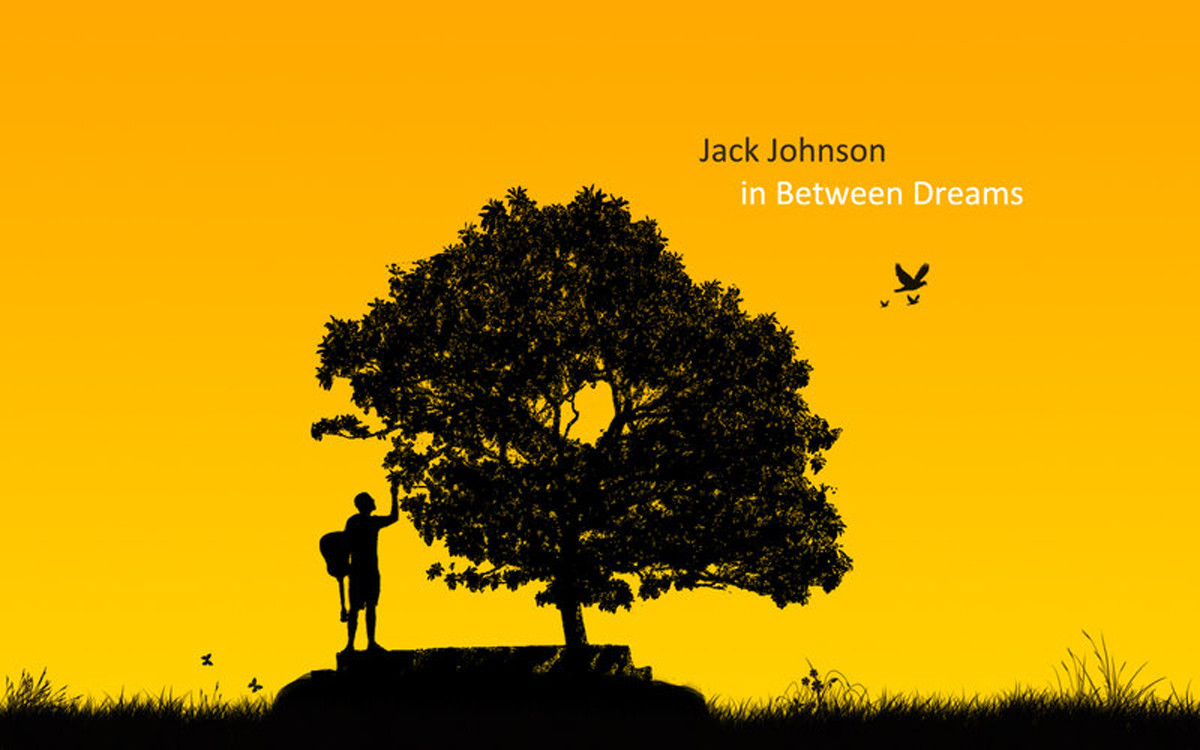Industrialization and Craftsmanship

20世紀の工業デザインに大きな影響を与え、ほぼ同時代に活躍したジャン・プルーヴェとフィン・ユール。2人のデザイナーの2つの展覧会を梯子しました。
Wooden Church and Chapel on the Water

札幌の聖ミカエル教会は、アントニン・レーモンドの設計で1960年に建てられました。上部のハイサイドから柔らかい光が落ちてきます。
S,M,XL-Tokyo Office Story

毎年恒例の芸術学校の建築セミナー、今年の第1回はTokyo Office Storyと称して東京の3つのサイズ「S,M,XL 」のオフィスを見学するツアーでした。
Real estate in Kitamoto

「おもしろ不動産お披露目会」北本市内の廃屋、空き店舗、倉庫から、空き地や畑、森、駅まで、まちに眠る魅力ある場所を地域資源ととらえ、「おもしろ不動産」として活用していくアートプロジェクト。